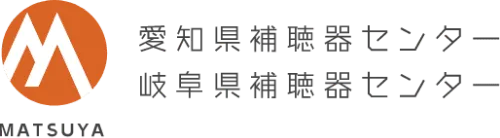公開日:
更新日:
補聴器を使用している方もそうでない方でも、補聴器の仕組みがどうなっているのかと不思議に思う方がいらっしゃるのではないでしょうか?
最近では、補聴器は外から入ってきた音をただ大きくするというだけでなく、音を細かく分析し、聞きやすくなるように調整する機能も備わっています。
そこで本記事では、補聴器の仕組みがどうなっているのかを種類や形状ごとに解説していきます!
補聴器の購入を検討中の方は、下記の文章を参考に補聴器の仕組みを理解し、補聴器選びの参考にしてください。
補聴器の種類とその仕組み

補聴器にはさまざまな分類の仕方がありますが、まず大枠として、デジタル補聴器とアナログ補聴器の2種類が存在し、デジタル補聴器の1つである骨伝導補聴器も、最近は種類の1つとして販売されています。
以下で、デジタル補聴器とアナログ補聴器、骨伝導補聴器の仕組みについて解説していきます。
デジタル補聴器
「デジタル」とはもともと、量や情報を、 段階的な物理量や連続的に変化する別の量に対応させて表すことを言い、情報の正確性が高いという特徴があります。
デジタル補聴器は、マイクで取り込んだ音をデジタル信号として処理している補聴器です。
拾った音を大きくするだけでなく、雑音を抑制し、聞きたい音を強調したり、周囲の環境に併せて聞こえ方や音量を自動で変更することも可能です。
また、デジタル補聴器は小さなICチップを使用しているため、劇的に小型化を遂げ、人々の生活により一層溶け込みやすくなっています。
アナログ補聴器
「アナログ」は連続した量(例:時間)を他の連続した量(例:角度)で表示することで、曖昧な情報も伝えること(例:アナログ時計)ができるという特徴があります。
アナログ補聴器は、マイクから伝わる電流をトランジスタなどで物理的に増幅して音を大きくする補聴器です。
アナログ信号を用いてマイクで取り込んだ音の増幅や調整を行い、聞こえをサポートする仕組みとなっており、この仕組みと構造がシンプルなので、音質の調整や加工ができる幅は少ないです。
骨伝導補聴器
骨伝導とは、頭蓋骨に振動を与え、「外耳」「中耳」を飛ばして直接内耳を刺激して聞く音のことを指します。
骨伝導補聴器は、この骨伝導の仕組みを活かして、耳周辺の骨部分に振動子(レシーバー)を当て、直接頭蓋骨(側頭骨)に振動を与える仕組みです。
この振動が直接内耳に届き、音を感知することができるようになっています。
内耳より奥には問題なく、外耳から中耳にかけての伝音器に障害があるという方は、直接内耳に働きかけることができる骨伝導補聴器が向いています。
最近の補聴器はほとんどがデジタル補聴器

近年では、販売されている補聴器のうち実に9割以上がデジタル補聴器であると言われています。
以下では、アナログ補聴器よりもデジタル補聴器が一般的になっている理由を見ていきましょう。
デジタル補聴器は一人ひとりに合わせて適切な調整ができる
デジタル補聴器は音を分析・処理する技術が高いため、単純に音を大きくするというだけでなく、補聴器を使う人それぞれに合わせて音を調整することができます。
補聴器を使用する方はそれぞれ難聴の原因や度合いも違えば、症状や聞こえにくい音も異なるでしょう。
聴力測定のデータを基に、一人ひとりに合わせて適切に調整された聞こえとなっているのは、大きな魅力です。
アナログ補聴器はシンプルな分音の小さな調整ができない
アナログ補聴器は、仕組みや構造自体がシンプルとなっています。
そのため、曖昧な音の情報が削除されており、デジタル補聴器に比べて音が足りていません。
そのため、細かな音の調整をすることができず、小さな音を聞こえるようにすると大きな音が響きすぎるといった問題点があります。
補聴器が音を大きくする仕組み

では、補聴器の仕組みについて、最近の主流であるデジタル補聴器を例に見ていきます。
補聴器は、簡単に言うと、①マイクで音を取り込み、②コンピューターで音を処理し、③スピーカーで音を出力するという3つの仕組みで成り立っています。
ちなみに、アナログ補聴器も仕組みとしては同じであり、大きな違いはマイクで取り込んだ音をコンピューターで処理するか、アンプで増幅するかです。
①マイクで音を取り込む
外から入った音は、高感度・高性能なマイクを使用して補聴器に入る仕組みとなっています。
最新のデジタル補聴器では「無指向性マイク」と「指向性マイク」の2つのマイクを搭載し、音を拾う範囲を調整しているものもあります。
マイクには補聴器に入ってきた音を電気信号に変換する働きがあり、変換された電気信号はアンプへ音をつなげます。
②コンピューターで音を処理
マイクから届いた音は、コンピューターで電気信号として処理され、音を増幅させます。
また、近年では音を大きくするだけではなく、大きさや方向・音域を分析して、必要な音を作り出す機能が備わっています。
さらに、音を調整するときに不要な雑音を取り除き、より快適な聞こえを得られるようにもなっています。
③スピーカーで音を出力
コンピューターに伝達されて調整された電気信号は、再び音に戻され、スピーカーから鼓膜に届けられます。
最近ではかなり小型な補聴器が開発されていますが、その中にもこれだけの仕組みが内蔵されていることで、快適に音を調整することが可能となったのです。
補聴器の形状

補聴器にはデジタル補聴器・アナログ補聴器の2種類があるとお伝えしましたが、補聴器の形状でもいくつかの種類が存在します。
以下では、補聴器の形状を大きく分けて3種類ご紹介します。
耳あなタイプ
耳あなタイプは、耳穴の中に収まるタイプの補聴器で、使用する方一人ひとりの形状に合うように作成されます。
小型・軽量であることが魅力で、耳の収音機能を活かすことが可能であり、眼鏡やマスクと干渉しないため、脱着し易いのも特長です。
一人ひとりの「扱いやすさ」「装用感」「見た目」「ライフスタイル」に合わせるために様々な形や大きさが販売されており、電池交換不要な充電式もあります。
耳かけタイプ
耳かけタイプは、補聴器本体を耳の上にかけて使用するタイプの補聴器で、軽度~重度難聴まで対応が可能です。
耳あなタイプに比べて操作が簡単で、電池交換不要な充電式もあります。
とても小さく、カラフルでおしゃれなデザインも多いのも魅力の1つです。
ボックスタイプ
本体から伸びたコードの先にイヤホンがついており、このイヤホンを耳に入れて操作するのがボックスタイプの補聴器です。
スイッチやボリュームが比較的大きいため、操作しやすいのが特長で、マイク内蔵型の製品であれば、話し手に本体を向ける事で聞き取りやすくなります。
しかし、音をよく拾うので快適に使い辛いことや、コードがあるため取り扱いに注意が必要な点がデメリットとして挙げられます。
適切な補聴器は補聴器専門店で選ぼう!

補聴器には種類があり、近年普及しているデジタル補聴器は、その複雑な仕組みによって高い性能を保持していることが分かりました。
また、補聴器は大きく分けて3種類の形状があり、それぞれの特長も異なります。
自分に最適な補聴器を見つけたいという方は、補聴器専門店がおすすめです。
豊富な知識と経験を活かし、幅広い種類の補聴器の中から最も適した補聴器を提案してくれるでしょう。
補聴器の購入なら補聴器センターで!
愛知県補聴器センター・岐阜県補聴器センターでは、補聴器の相談・体験を無料で行っています。
お客様の現在の聞こえの状態や、どのような過程で聞こえにくくなったのか、どんな時に聞こえづらくてお困りになっているのかを伺いながら、専任のスタッフが補聴器選びのお手伝いをいたします。
無料で補聴器の音質調整や点検・クリーニングも行っていますので、ぜひお気軽にお近くの補聴器センターにお越しください!
補聴器の仕組みはどうなってる? まとめ

本記事では、補聴器の種類や仕組みについて解説しました。
補聴器の仕組みについて理解したことで、より自分に合った補聴器を選ぶことができるのではないでしょうか。
紹介した、耳あな型・耳かけ型・ポケット型以外にも、充電式や電池式などの様々な種類の補聴器が存在します。
自分に最適な補聴器を選びたいという方は、ぜひお近くの補聴器専門店に足を運んでみてください。
愛知県補聴器センター・岐阜県補聴器センターでは、経験豊富な補聴器専門相談員がカウンセリングを重ね、お客様に最適な補聴器をご提案をしております。
出張手数料無料でご自宅や介護士施設へ伺うサービスも行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
お近くの補聴器センターを探す