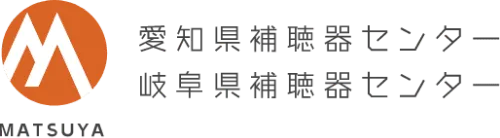公開日:
補聴器は、聴力の低下にお悩みの方々の生活の質を向上させる貴重な医療機器です。
しかし、正しい使い方を知らなければ、補聴器の十分な効果を得られないばかりか、さまざまなトラブルを引き起こす可能性もあります。
本記事では、補聴器をご使用の際に留意すべき点について詳しく解説いたします。
補聴器を初めて使用される方はもちろん、長年お使いの方も、無意識のうちに誤った使用をしていないか、ご確認いただくことをおすすめします。
補聴器の重要性と正しい使い方の重要性ついて

補聴器は、音や声が聞こえにくい方にとって、人との会話を円滑にするだけでなく、生活音を正しく認識するためにも重要な管理医療機器です。
しかし、補聴器を使い始めたばかりの方にとっては慣れない機器でもあるため、生活で当たり前に行っていたことが故障の原因になってしまっていたり、そもそも使用方法が間違っていて性能を発揮できていない可能性があります。
さらに、長期間ご使用されている場合でも、管理方法が適切でないと、故障の原因となる可能性があります。
十分な効果を発揮させ、故障を引き起こさないためには、正しい使い方や使用上の注意点を予め知っておくことが重要となります。
補聴器の取り扱いに関する3つの重要な注意点

ここでは、補聴器を取り扱う際に特に注意すべき3つのポイントについて解説します。
ご自身が誤った取り扱いをしてしまっていないか、確認してみてください。
補聴器取り扱いの注意点①就寝時には補聴器を外す
補聴器を使い始めたばかりの方の中には、慣れるために24時間つけっぱなしにしているという方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、補聴器は基本的に起きている間の使用が想定されている機器であるため、就寝時の装着は推奨できません。
補聴器を長時間装着すると、耳の通気性が悪化し、補聴器内部に湿気が蓄積しやすくなるため、故障のリスクが高まります。
また、耳の炎症や寝返りによる痛みを招いたりと、ご自身の体にも悪影響を及ぼす可能性があります。
就寝時は補聴器を外し、電池ケースを開けて内部の湿気を逃がしておきましょう。
補聴器取り扱いの注意点②レントゲン撮影時には補聴器を外す
医療機関でのレントゲン撮影時には、基本的に補聴器を外す必要があります。
補聴器が画像に映り込んで診断の妨げになったり、X線が補聴器の電子回路に影響を与える可能性があるためです。
これはCT検査やMRI検査の場合も同様であり、特にMRIは強力な磁気を使用するため、補聴器に深刻なダメージを与える恐れがあります。
検査前に医療スタッフへ補聴器の使用を申告し、取り外した補聴器は紛失しないよう、安全な場所に保管してください。
補聴器取り扱いの注意点③ハウリングが起こらないようにする
ハウリング(キーンという音)は、補聴器のマイクで拾った音が増幅され、再びマイクに戻るのが要因で発生する現象です。
このハウリングが生じると、ご自身が不快なだけでなく周囲の方にも聞こえてしまい、思わぬトラブルを招く可能性があります。
ハウリングが生じた際は、以下の方法で適切に対処しましょう。
- 補聴器が正しく装着されているか確認
- 補聴器の位置を微調整
- 耳や補聴器の清掃
- 音量を少し下げてみる
上記の方法を行っても頻繁に発生する場合は専門家に相談する事をおすすめします。
補聴器に関する疑問や不安がございましたら、お近くの補聴器センターへお気軽にご相談ください。
補聴器のメンテナンス・お手入れ上の注意点

補聴器を長く使い続けていくには、正しいメンテナンスやお手入れを行うことも重要です。
補聴器の使用に慣れている方も、ご自身のお手入れ方法が正しいかを確認しておきましょう。
お手入れは優しく丁寧に行う
補聴器のお手入れを行う際には、専用ブラシやクロスを使って、本体や音の出入口部分の汚れを優しく除去するクリーニングを行いましょう。
特に音の出口(レシーバー部分)は耳垢が詰まりやすいので、定期的な清掃が重要です。
ただし、強い力を加えると内部の精密部品を傷める可能性があるので注意しましょう。
補聴器の電池切れに注意
補聴器を使用する際には、外出先で電池切れを防ぐため、定期的に電池を交換することが大切です。
補聴器の電池の寿命は以下のようになっています。(※Bluetooth機能の使用頻度や音量設定によって電池寿命は変動します。)
- 10番電池(PR536):3〜5日
- 13番電池(PR48):10〜14日
- 312番電池(PR41):5〜8日
- 675番電池(PR44):10〜14日
補聴器は電池残量が少なくなると警告音が鳴る機種も多いため、早めの交換を心がけましょう。
予備の電池は常に携帯しておくと安心です。
定期的に専門店でメンテナンスを行う
補聴器は1〜3ヶ月に一度、専門店でプロフェッショナルなクリーニングと機能チェックを受けることをおすすめします。
補聴器専門店では、特殊な機器を使って内部の汚れを除去し、音質や増幅レベルの確認を行うことが可能です。
定期メンテナンスは故障予防にもつながりますので、ぜひお近くの補聴器センターにお立ち寄りください。
水濡れは厳禁!湿気は故障の原因に
補聴器は精密機器のため、水濡れや湿気は故障の原因になります。
入浴時には必ず外し、水洗いは絶対にしないようにご注意ください。
また、少量の湿気でも故障に繋がるため、就寝前には専用の乾燥ケースに入れて保管しましょう。
UV除菌機能付きの電子乾燥ケースや、補聴器全体を覆う布製のカバーを使用するのもおすすめです。
なお、補聴器の中には防水機能を搭載した製品もあります。
運動を行う習慣がある方などは、防水補聴器を選択しましょう。
補聴器を正しく使用する方法

続いて、補聴器を正しく使用する方法を解説していきます。
補聴器を長く使い続けるために、以下の点を意識しておきましょう。
補聴器を正しく装着する
補聴器を正しく使用するためには、まず装着方法が合っているのかを確認しましょう。
まず装着前には手を清潔にし、補聴器の電源はオフの状態で、鏡を見ながら装着します。
装着後は「ご自身の声が自然に聞こえるか」「周囲の音や声が適切に聞こえるか」をチェックし、正しく装着できているかを確認しておきましょう。
正しい装着方法は、快適な聞こえを得るためにも非常に重要なポイントです。
補聴器の種類に合わせた装着方法のポイントを下記にまとめているので、こちらも合わせてご確認ください。
耳かけ型補聴器の装着ポイント
- 本体を耳に掛ける
- イヤモールドやドームを耳穴に優しく挿入する
- チューブが耳に沿うよう位置を調整する
- 本体が安定して収まっているか確認する
耳あな型補聴器の装着ポイント
- 右耳用・左耳用を確認する
- 小さな突起や取り出し用の手ぐすが外側になるよう向きを確認する
- 先端を耳の穴に当てフィットするよう挿入する
- しっかり固定されているか確認する
正しい音量調整を行う
補聴器を使用するに当たっては、正しい音量調整で使用する事も重要です。
音量調整が適切でないと、せっかくの補聴器の性能が発揮できないことにもつながります。
補聴器初心者の方は、初めは静かな環境で低めの音量から始め、「聞こえるけれど、うるさくない」レベルの音量調整を目指しましょう。
最新のデジタル補聴器は環境に応じた自動調整機能がありますが、手動調整も覚えておくと便利です。
補聴器に慣れるまでの期間(1〜3ヶ月)は定期的に補聴器専門店などで相談しながら微調整を行うと良いでしょう。
使用感や困りごとを具体的に伝えると、より快適な設定に近づけられます。
補聴器に関するよくある質問と対処法
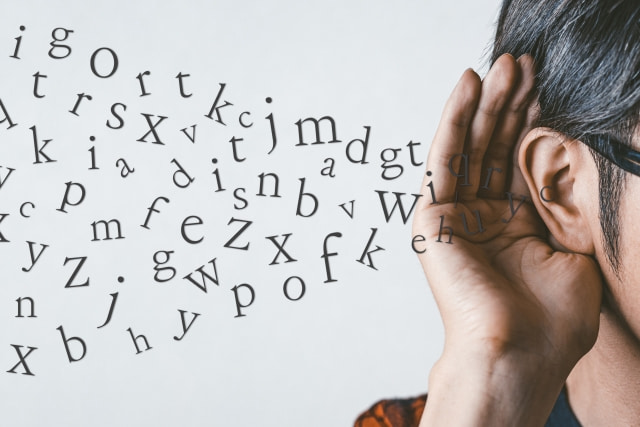
最後に、補聴器の注意点についてよくある質問にお答えしていきます。
その他、ご不明点がございましたら、お気軽に店舗へご相談ください。
Q: 補聴器をつけながらイヤホンは使えますか?
A: 補聴器のタイプや、イヤホンの種類によって対応方法が異なります。
補聴器とイヤホンを同時に使用したい場合は、
- Bluetooth対応の補聴器を選ぶ
- 骨伝導イヤホンを利用する
- ネックループタイプの補聴器用アクセサリーを使用する
といった方法があります。
ご自身の補聴器や生活スタイルに合った方法を専門店に相談しましょう。
Q: 補聴器に電磁波の影響はありますか?
A: 補聴器は電子機器のため、強い電磁波の影響を受ける可能性がありますが、最新の補聴器は対策が施されており、日常生活で大きな問題になるケースは少なくなっています。
空港のセキュリティゲートや防犯ゲートは、通過するだけなら心配ありません。
しかし、IH調理器や電子レンジなどへ極端に近づくと異音がする場合があるので注意が必要です。
ご自宅の無線LAN機器の影響で補聴器の使用に支障があることもあります。その際は、無線LAN機器の置き場所にも工夫が必要です。
Q: 補聴器をつけると耳が悪くなるって本当?
A: 補聴器の使用によって耳が悪くなるというのは誤解です。
多くの難聴は進行性であるため、補聴器使用と無関係に悪化する可能性があります。
また、適切な装着方法や音量調整がされていない場合には不快感を感じることがあるため、本記事で解説した正しい装着方法を心がけましょう。
適切に調整された補聴器の使用は、コミュニケーション能力の維持や脳の活性化に役立ちます。
補聴器に関する注意点を徹底解説! まとめ
補聴器は、正しく使えば、音や声の聞き取り改善だけでなく生活の質を大きく向上させる大切な管理医療機器です。
補聴器をご使用の際は、本記事で解説した注意点を踏まえ、正しい使用方法と管理を心がけましょう。
最適な補聴器選びから日々のケア、トラブル対応まで、正しい知識を身につけるのが快適な補聴器ライフへの第一歩となります。
補聴器に関するご相談やご質問がございましたら、ぜひお近くの補聴器センターへお問い合わせください。